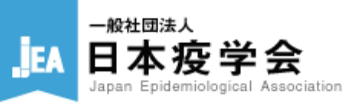日本語版Highlights
Volume 28, Issue 1-12 (2018)
Issue 12 (December 2018)
Issue 11 (November 2018)
Issue 10 (October 2018)
Issue 9 (September 2018)
Issue 8 (August 2018)
Issue 7 (July 2018)
Issue 6 (June 2018)
Issue 5 (May 2018)
Issue 4 (April 2018)
Issue 3 (March 2018)
Issue 2 (February 2018)
Issue 1 (January 2018)
Volume 28, Issue 12 (December 2018)
- EdAlプログラムは男児の肥満有病率減少のための費用対効果の高いものであった。
- 費用対効果に関する検討は肥満有病率に加え、複数の指標を用いた。
- 4.39%の有病率低下のために、男児1人あたり年間5.21ユーロを要した。
- EdAlプログラムはその費用対効果より持続可能性のあるプログラムであった。
- 食事記録とFFQの間で分位数の一致度をみる重み付けκ係数は高かった。
- 再現性をみる2回のFFQの相関係数は中程度だった。
- FFQで推定したアクリルアミド摂取量は、がんとの関連を検討する際には順序データとして用いることが適している。
- アクリルアミド摂取量を推定する上では、調理方法を考慮することが重要である。
- ベトナム、カインホア省にてデング熱の血清疫学調査を実施した。
- 農村部の血清陽性率は都市部と同等に高かった。
- 家屋が密集した地域への近接性は、IgGとIgMの陽性に共通したリスク要因であった。
- 母親の妊娠初期の体重は、思春期における子どもの体重と関連していた。
- この関連は、出生時や3歳時の子どもの体重との関連よりも強かった。
- 母親の生活習慣が思春期の子どもの体重に影響を与えている可能性が示唆された。
- 日本におけるコーヒー摂取と大腸がんに関する新しいメタアナリシスの結果を示した。
- 2段階変量効果モデルを用いた用量反応関係のメタアナリシスを実施した。
- この解析によって、コーヒーの摂取量に応じたリスクを明らかにすることができた。
Volume 28, Issue 11 (November 2018)
Special Article
Japanese Legacy Cohort Studies: The Hisayama Study
Japanese Legacy Cohort Studies: The Hisayama Study
- 久山町研究は地域住民を対象とした前向きコホート研究であり、生活習慣病の危険因子を明らかにすることを目的としている。
- 研究テーマは、心血管病、認知症、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病などと多岐にわたる。
- 本研究は、様々な生活習慣病やその危険因子の有病率や罹患率の時代的変化に関する報告をしてきた。
- 今後も研究を継続することで、人々の健康長寿の実現に貢献することが期待される。
- グループ活動に参加することで高齢者の健康が向上することが知られている。
- 所属するグループに多様な背景を持った人が参加しているかどうかで、どのように健康と関連するのか不明であった。
- 本研究により、グループ内のメンバーの多様性が高いほど主観的健康感が良い人が多い、という関連が明らかになった。
- グループ内に男女が共にいることが、特に良い主観的健康感と関連していた。
- 学歴は最も重要な健康の社会的決定要因の一つである。
- 日本における縦断調査によって3つの高校中退の決定要因が明らかとなった。
- 高校中退に至った者は、中学生時に、遅刻が多く、喫煙するようになり、そして虐待やネグレクトなどの困難を抱えていた。
- 中学生において、これらの要因を発見した場合にはその問題に対処するだけでなく、高校中退に至るハイリスクグループとしてケアしていく必要があると考えられた。
Short Communication
Cumulative Risk of Type 2 Diabetes in a Working Population: The Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study
Cumulative Risk of Type 2 Diabetes in a Working Population: The Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study
- 勤労者において糖尿病の累積罹患リスクを推定した。
- 30歳の男性の3分の1、女性の5分の1が65歳までに糖尿病に罹患する。
- 過体重と肥満によって糖尿病のリスクはかなり高まる。
- 平成23年患者調査と医療施設調査の個票データを突合し、がん入院患者の受療行動についてGISによる運転時間を用いて分析した。
- 胃がんや大腸がんの患者は他のがんに比べて近い病院に入院しており、子宮頸がんや白血病の患者はより遠方に入院している傾向にあった。
- 年齢が若い患者、また居住する二次医療圏にがん診療拠点病院がない患者はより遠方の病院に入院している傾向にあった。
Volume 28, Issue 10 (October 2018)
- 日本の小学生児童を対象に長時間メディア利用の関連要因を検討した。
- 長時間メディア利用の児童は、両親のネット使用(2時間以上/日)、家庭内でのルール無いことに有意に関連した。
- 母親の健康習慣が悪いことも、児童の長時間メディア利用の関連要因であった。
- カフェイン推定摂取量と血清葉酸値との関連が見られた。
- カフェイン/タンニンの(推定)摂取量と血清葉酸の値には負の関連が認められた。
- 妊婦は、コーヒー・紅茶だけでなく、緑茶を含むカフェイン飲料の多飲に、注意が必要であると思われる。
- 一般集団における乳癌患者の長期予後が近年改善しているか否かを、日本人口の13.4%を占める地域がん登録データを用いて検討した。
- 1993年から2006年の間に、5年相対生存率は2.8%、10年相対生存率は2.4%の改善を認めた。
- これらの生存率の改善は、35-69歳において35歳未満や70-99歳より大きく、領域群において限局群や遠隔転移群より大きかった。
- 食物摂取頻度調査票(FFQ)に基づく食事由来の抗酸化能の妥当性と再現性を検討した。
- FFQに基づく食事由来の抗酸化能の推定値は中程度の妥当性と再現性が認められた。
- FFQに基づく食事由来の抗酸化能のカテゴリ分類は、DRに比べて過度な誤分類は示されなかった。
- FFQによって推定された食事由来の抗酸化能をカテゴリ分類し、疾病との関連を検討することは役立つだろう。
Short Communication
Simultaneous Validation of Seven Physical Activity Questionnaires Used in Japanese Cohorts for Estimating Energy Expenditure: A Doubly Labeled Water Study
Simultaneous Validation of Seven Physical Activity Questionnaires Used in Japanese Cohorts for Estimating Energy Expenditure: A Doubly Labeled Water Study
- 日本の大規模疫学コホートで用いられている身体活動質問票7種の妥当性を、二重標識水法を基準として検証した。
- 総エネルギー消費量に関して、すべての質問票で中程度から強い相関が認められた。
- 身体活動質問票の総エネルギー消費量に関する妥当性は、活動量計と比べて決して劣るものではなかった。
Volume 28, Issue 9 (September 2018)
- 握力は認知機能と横断的および縦断的に関連する。
- 手の器用さは認知機能と横断的に関連する。
- 手の器用さと認知機能との縦断的な関連は不明である。
- 握力と手の器用さどちらが縦断的に認知機能により強く影響を及ぼすかは明らかではない。
- 握力、手の器用さおよび認知機能の相互関連性は不明である。
- ウイルス学的検査に基づく食品に由来するノロウイルス感染症流行データを再分析した。
- 全サンプルを通じた不顕性感染比率は32.1%と推定された。
- ノロウイルス遺伝子型GII.4の感染時における不顕性感染比率は40.7%と推定された。
- 得られた推定値は遺伝子型GII.4による流行の制御が実践的にも困難であることを裏付けるものであった。
- 追跡期間18年を超える日本人の大規模コホート研究。
- 女性で食事からの抗酸化ビタミン摂取が全死亡低下に働く。
- 抗酸化ビタミンと死亡との負の関連は特に女性の非喫煙者で認められた。
- 259名日本人を対象とした前向き追跡研究を行った。
- トマトの摂取頻度が握力の3年間の変化と逆相関を示した。
- トマトを積極的に食べることが握力低下の予防につながる可能性が示唆された。
Volume 28, Issue 8 (August 2018)
- 本人の教育歴と口腔の健康状態の関連は、独身女性においてみられ、既婚女性ではみられなかった。
- 既婚女性において、配偶者の教育歴と口腔の健康状態の関連はみられなかった。
- 既婚女性、特に専業主婦において、所得と口腔の健康状態の関連がみられた。
- 2型糖尿病発症リスク予測モデルを東アジア人の長期間追跡データに基づいて開発した研究報告は比較的少ない。
- 我々は10年以内に2型糖尿病を発症する確率を予測するリスクスコアを日本人中年男性において開発した。
- このリスクスコアは、2型糖尿病発症のハイリスク者を同定するために用いることができるかもしれない。
- ラトビア人集団を対象にした遺伝情報データベースはオープンな研究プラットフォームである。
- 人口規模の小さな国における全国規模のバイオバンクは疫学研究に有用である。
- バイオバンクは遺伝的検査やヘルスケアの進歩に大きく貢献している。
- バイオバンクは研究における生体試料の需要に関して予見し、計画的に当たる事が重要である。
- バイオバンクに対する経済的なサポートは、国、研究そのもの、あるいは企業からの何れもが想定できる。
- メタボリックシンドロームの肥満以外の因子の有無により区別した「代謝的に健康、代謝的に不健康」と肥満の有無とを組み合わせ、蛋白尿発症との関係を調べた。
- 代謝的に健康な肥満者は蛋白尿発症リスクの上昇を認めなかった。
- 肥満の有無にかかわらず代謝的に不健康な者は蛋白尿発症リスクの上昇を認めた。
- Adiponectinとがん死亡および全死亡の関連を地域在住高齢者コホート(n=697)から検討した。
- 血漿Adiponectinとがん死亡および全死亡の間には非線形の有意な正の関連がみられた。
- 本結果から複雑な機序の存在が示唆され、さらなる検討が必要である。
Volume 28, Issue 7 (July 2018)
- 高齢者の独り暮らしは精神健康悪化のリスクであることはよく知られている。
- 居住形態と精神健康の関連に関する縦断調査はほとんど実施されていない。
- 居住形態と精神健康の関連に対する近隣居住地域における社会的結束の影響を検討した研究は、ほとんどない。
- 高齢者において、居住形態は抑うつ症状発症のリスクに影響を与える。
- ジェンダーならびに居住近隣地域の社会的結束レベルは、居住形態と抑うつ症状発症リスクの関連に影響を与える。
- タイのコンケンの地域がん登録データの解析を行ったところ、1995から2012年の間に、同地域における乳がん年齢調整罹患率上昇が認められた。
- 同地域において、特に50歳以上の女性における乳がん年齢調整罹患率の上昇が際立っていた。
- 同地域ににおける乳がん増加傾向はタイの他の地域よりも小さいが、2030年までに著明に増加する事が予測される。
- 低出生体重は中年期以降の慢性疾患のリスク増加と関連している。
- 子どもの頃の身体活動はこの関連を一部説明する可能性がある。
- 日本の児童生徒における出生体重と身体活動の関連を検討した。
- 男子では関連がみられなかったが低出生体重で出生した女子は身体活動を実施している割合が少なかった。
Short Communication
Sleep Duration Modifies the Association of Overtime Work With Risk of Developing Type 2 Diabetes: Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study
Sleep Duration Modifies the Association of Overtime Work With Risk of Developing Type 2 Diabetes: Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study
- 残業時間と2型糖尿病発症との関連について、日本の労働者を対象に検証を行った。
- 残業時間が長くても糖尿病発症リスクは高まらなかった。
- しかし、長時間残業でかつ睡眠時間が短い人では糖尿病発症リスクの増加を認めた。
Volume 28, Issue 6 (June 2018)
- 女性の過体重および肥満が年々貧困層に集中している傾向。
- 女性では、半島部においては富裕層に肥満が多い。
- 中国人女性は肥満が少なく、その増加も少ない。
- 男性では、半島部では貧困層における肥満の集中が減少傾向。
- 半島部では東部に比べて肥満は富裕層に多い傾向。
- 東洋医学において黄苔(黄色い舌の苔がある状態)は糖尿病の臨床所見の一つとして用いられてきている。
- 黄苔を有している人は黄苔がない人に比べ、糖尿病の有病率が有意に高かった。
- 黄苔を有している人は黄苔がない人に比べ、境界型糖尿病の有病率が高い傾向を認めた。
- 肥満および身体不活動は心血管疾患のリスク増大をもたらす。
- 不活動な人におけるうつ病のリスクは体重とは独立している。
- 肥満とうつ病の関連は変更可能なリスクファクターの影響を受ける。
- 1998年から2015年までの期間における母乳中ダイオキシン類レベルの年次推移を観察した(n=1194)。観察期間中、母乳中ダイオキシン類レベルは減少傾向を示した。
- ただし、直近5年間では下げ止まり(横ばい)の傾向を示した。
- 一方で、直近5年間における母乳提供者の平均年齢は高くなる傾向を示した。
- 年齢が高いほど母乳中ダイオキシン類レベルは有意に高かった。
- 日本ではダイオキシン類のヒトへの曝露が最小限のレベルに近づきつつあると推察できる。
- 人口動態統計出生票と乳児死亡票を連結した。
- 児の社会的リスク因子と医学的リスク因子の双方とも事故死のリスク、病死のリスクに影響を与えていた。
- 社会的・医学的リスク因子のいずれをもつ児に対しても、社会的サポート、医学的サポートの双方を提供することが重要である。
Volume 28, Issue 5 (May 2018)
Review Article
A Literature Review of Mathematical Models of Hepatitis B Virus Transmission Applied to Immunization Strategies From 1994 to 2015
A Literature Review of Mathematical Models of Hepatitis B Virus Transmission Applied to Immunization Strategies From 1994 to 2015
- B型肝炎の流行を模した動的伝播モデルには短所がある。
- よくあるモデルは正確なデータの取得に欠点がある。
- 年齢構造モデルを十分に考慮すべきである。
- 年齢と時間に依存したB型肝炎ウイルス感染力を十分に考慮すべきである。
- 「健康づくりのための身体活動基準2013」で推奨されている全身持久力の基準を数年間継続的に達成することは、2型糖尿病罹患の低いリスクと関連する。
- 全身持久力の基準を継続的に達成することは、基準を一時的に達成することより2型糖尿病罹患の低いリスクと関連する。
- 全身持久力の基準は、2型糖尿病の予防に対しておおよそ妥当な基準であると考えられる。
- 東日本大震災の被災により、乳幼児の成長は影響を受けたかもしれない。
- この研究では、被災した乳幼児と被災していない乳幼児のBMI・体重・身長の変化を比較した。
- 震災後、福島県の小児でBMIの上昇が月齢42ヶ月に至るまで観察された。
- 福島県の子どもの一部に成長障害が起こっている可能性がある。
- 小児科医師は、これらの子どもが将来肥満にならないかを注意深く見守る必要がある。
- 日本の大規模コホート研究を用いたプール解析により、34万人以上を対象にbody mass index(BMI)と膵臓がん罹患との関連を評価した。
- アジア人においてもBMIと膵臓がんには関連がある可能性が示された。
- 男性では肥満(≥30 kg/m2)が膵臓がん罹患リスクを有意に上昇させた。
- 男性では20歳時BMIと膵臓がん罹患にJ字型の関連がみられた。
- 全身肥満は、骨への効果を有する。
- 研究結果は心外膜下脂肪が有する骨への有益な効果を支持しない。
- 観察された結果は心外膜下脂肪と骨塩量との遺伝的関連を示唆する。
- 日本人成人は、多くの時間を座位行動に費やしている。
- 座位行動の3分の1以上は、時間が30分以上継続していた。
- 日本人成人は、10分以上持続する身体活動を行う時間は、極めて少ない。
- 対象者の過半数(65.2%)は身体活動のガイドラインを満たしていなかった。
- 座位行動と身体活動の両方の行動に焦点を当てた介入は、ポピュレーションレベルで必要とされる。
- 日本人男性労働者7804人を最大23年間追跡した。
- 全身持久力は20年以上の長期間にわたって2型糖尿病罹患と関連した。
- 全身持久力と2型糖尿病罹患の関連は追跡期間が長くなっても弱まらなかった。
Volume 28, Issue 4 (April 2018)
Special Article
Japanese Legacy Cohorts: The Life Span Study Atomic Bomb Survivor Cohort and Survivors’ Offspring
Japanese Legacy Cohorts: The Life Span Study Atomic Bomb Survivor Cohort and Survivors’ Offspring
- 寿命調査は、原爆被爆者の生涯の健康帰結を調査する比類のない大規模コホート研究である。
- 寿命調査は、原爆放射線による悪性疾患のリスク増加を確認し、他の健康後影響を調査してきた。
- 胎内被爆者では若年被爆者と同様の健康後影響がある。
- 親が被爆後に受胎した子ども(被爆二世)のコホートでは、今のところ、がんおよび非がん疾患のリスク増加はみられない。
- これらのコホート調査の結果は日本政府により被爆者および被爆二世の健康管理および福祉に使用されてきた。
- 寿命調査の結果は、放射線被ばくによる定量的リスク推定値の最も信頼できる情報源と認められ、世界で使用されている。
Review Article
Tobacco Control Measures to Reduce Socioeconomic Inequality in Smoking: The Necessity, Time-Course Perspective, and Future Implications
Tobacco Control Measures to Reduce Socioeconomic Inequality in Smoking: The Necessity, Time-Course Perspective, and Future Implications
- タバコ対策が喫煙の社会格差へ与える影響に関する研究が進んでいる。
- タバコ増税は所得に応じた喫煙格差を減少させると先行研究で明らかになった。
- 喫煙の社会格差を減らすために、逆進的格差推移仮説(Inverse equity hypothesis)がキーになるかもしれない。
- タバコ対策はどれも長期間継続させることにより、喫煙の社会格差を減少させられる可能性がある。
- 喫煙の社会経済格差の問題は、公衆衛生における重要な課題のひとつである。
- 一般集団における「めまい」の1年有病率は、20.10%であった。
- 「めまい」は、女性と高齢者に多かった。
- 「めまい」は、血液中の中性脂肪が高い人や歩行障害のある人に多かった。
- 「めまい」は、喫煙者、飲酒者、うつ病、ストレスの多い人に多かった。
- 「めまい」に対しては、多元的な対応をすべきである。
- アルコール摂取量と血清脂質の関連を検討した。
- またADH1BとALDH2 遺伝子多型による修飾を検討した。
- さらにALDH2遺伝子多型の所見について、再現性を検討した。
- 血清LDLコレステロールはアルコール摂取量増加とともに減少した。
- ALDH2遺伝子多型は、アルコール摂取量と血清LDLコレステロールの関連を修飾した。
- 食パターンの抽出にReduced rank regressionを用いた。
- 第一の食パターンは、メタボリック症候群の低い有病率と関連していた。
- 第一の食パターンは、高血圧および高血糖の有病率と負の関連があった。
- 就業者の約5 %にインターネット依存傾向が見られた。
- インターネットをゲームをする目的で使用する者に、インターネット依存傾向が多く見られた。
- 就業者に対してもインターネットの適正使用に関する啓発を行う必要性が示唆された。
- 今回の研究では、日本時集団におけるコーヒー摂取と全肺がんリスクの間に有意な関連はみられなかった。
- しかしながら組織型別の解析では、喫煙との関連が大きい小細胞肺がんリスクの上昇が示された。
- 喫煙状況層別解析におけるヘビースモーカーでの肺がんリスクの上昇は、喫煙の残交絡が考えられる。
- 肺がん組織型別の解析や、より詳細な喫煙曝露情報を含む研究の蓄積が望まれる。
- この研究は、毎年の視野検査によって労働者を追跡調査した最初の研究である。
- 視野異常の頻度は、長時間コンピューター利用する者に多かった。
- この関連は、特に屈折異常のある労働者にのみ認められた。
Volume 28, Supplement 3 (March 2018)
- H22年に全国で実施された国民健康栄養調査の参加者を対象にした前向きコホート研究NIPPON DATA2010を2010年に開始した。
- ベースライン時の評価項目は、身体計測、血液・尿検査、心電図、食事調査、社会経済因子等で、循環器疾患や糖尿病の発症・死亡、ADLやIADLについての予後追跡を行う。
- 成人女性では、低い教育歴は過体重・肥満と関連していた。
- 成人女性では、低所得は過体重・肥満と関連していた。
- 成人男性では、低い教育歴は肥満と負の相関を示していた。
- 社会経済的要因としての性差、年齢差は肥満有病率に影響を与える。
- 世帯収入は炭水化物摂取量と負に、脂質摂取量と正の関連を認めた。
- 食事摂取基準を超える高炭水化物・低脂質の食事を摂取する者は、高齢者に多かった。
- 世帯収入や世帯支出の低いもので、高炭水化物・低脂質の食事を摂取するリスクが高かった。
- 男女ともに低支出者層では穀物類の摂取量が多かった。
- 男性において低支出者層では乳類の摂取量が少なかった。
- 女性において低支出者層では野菜摂取量が少なかった。
- 男女ともに低教育歴者層では穀物類の摂取量が多かった。
- 男女ともに低教育歴者層では肉類の摂取量が少なかった。
- 日本人を対象として社会経済要因とナトリウムおよびカリウム摂取量の関連を調査した。
- 研究対象者は、2010年国民健康・栄養調査の参加者のうちNIPPON DATA2010研究への参加に同意を得られた者である。
- 摂取量の指標として、随時尿のナトリウムとカリウム濃度より推定した24時間尿中排泄量および随時尿中ナトリウム/カリウム比を用いた。
- 社会経済要因は、等価平均家計支出、教育年数、職業とした。
- 低い社会経済要因は、低い尿中カリウム量および高い尿中ナトリウム/カリウム比と関連を示した。
- 生活習慣の改善を実施している者は、高学歴(短大卒業以上)または中学歴(高校卒業以上)者に多かった。
- 生活習慣の改善を実施している者は、離婚した男女において少なかった。
- 循環器疾患危険因子を有する対象者は、生活習慣の改善を実施していた。
- 以上の関連は他の要因とは独立していた。
- 自宅での受動喫煙と社会経済要因との関連を検討した。
- 自宅での受動喫煙は、就業状況および低い教育歴と関連した。
- 受動喫煙対策は社会経済要因を考慮して進めるべきである。
- NIPPON DATA2010を用い、社会経済的水準と循環器疾患危険因子認知度の関連を検討した。
- 低学歴は循環器疾患危険因子認知度の低さと関連していた。
- 等価支出低値は循環器疾患危険因子認知度の低さと関連していた。
- 社会経済的要因と健診受診に関連がみられた。
- 特に、65-74歳についてその関連が確認された。
- 健診受診割合は、高学歴の者と持ち家居住者において高かった。
- 健診受診割合は、等価平均家計支出の高い者において低かった。
- 日本人集団において、教育歴と口腔の健康状態の関連がみられた。
- 日本人集団において、等価世帯支出と口腔の健康状態の関連がみられた。
- 行動学的・生物学的要因では、口腔の健康格差の全てを説明することはできなかった。
- 等価世帯支出と口腔の健康状態の関連は、高齢者でのみみられ、中年者ではみられなかった。
- 日本人成人において、教育年数が長いことと良好な主観的健康感の間には関連が認められた。
- 婚姻・世帯の状況と主観的健康観の間には、一貫した関連は認められなかった。
- 就労と主観的健康観の間に認められた関連は、年齢の調整によって消失した。
- 女性において、家計収入・等価平均家計支出が高いことは良好な主観的健康観と強く関連した。
Volume 28, Issue 3, (March 2018)
- ソーシャル・キャピタルの高い市区町村では、男性の抑うつの所得間格差が小さい。
- 失業率が高く、所得格差が大きいと感じる人が多い市区町村では、抑うつの所得間格差が大きい。
- 韓国人において飲酒パターンが空腹時血糖異常や糖尿病が認められた
- 男性において、ハイリスクな飲酒の頻度は、空腹時血糖異常や糖尿病のリスクと関連を示していた。
- 女性において、ハイリスクな飲酒の頻度は、空腹時血糖異常のリスクと関連を示していた。
- 男性において、非ハイリスクな飲酒の頻度は、高い糖尿病リスクと関連を示していた。
- 女性において、非ハイリスクな飲酒の頻度は、低い糖尿病リスクと関連を示していた。
- 妊娠12 週以降の先天異常の罹患率を報告した。
- 全先天異常の罹患率は出産1000 当たり18.9 であった。
- 全先天異常のうち9.4%は妊娠22 週未満の出産であった。
- 神経系の先天異常のうち39%は妊娠22 週未満の出産であった。
- 日本の非喫煙者で、受動喫煙に社会格差がみられた。
- たばこの害についての知識は、家庭での受動喫煙がすくないことに関連した一方、職場での受動喫煙には関連がみられなかった。
- 受動喫煙の社会格差縮小のために、比例的普遍アプローチにもとづく環境への介入が必要であろう。
- 本研究では飲酒と死亡リスクの関連について検討した。
- 飲酒と全死亡ではJ 字型の関連が見られた。
- 現在飲酒者では、飲酒量が増えるほど死亡リスクは線形に増加することが分かった。
- 休肝日はがんおよび脳血管疾患死亡と負の関連が見られた。
- 本研究から、休肝日を伴う適量飲酒の重要性が示唆された。
- 場面別座位行動尺度の信頼性および妥当性を検討した。
- 本尺度は許容可能な信頼性および妥当性が認められた。
- 本尺度は日本人がどのような座位時間を過ごしているかを評価することができる。
- 日本の子宮頸がん検診受診率は特に20代で低い。
- 子宮頸がん検診未受診の20歳女性に対して、様々な受診勧奨の方法について効果を検証した。
- 20歳女性に対する子宮頸がん検診受診勧奨の方法として、母親を介した受診勧奨が効果的であることが明らかとなった。
Volume 28, Issue 2 (February 2018)
Review Article
Critical Points for Interpreting Patients’ Survival Rate Using Cancer Registries: A Literature Review
Critical Points for Interpreting Patients’ Survival Rate Using Cancer Registries: A Literature Review
- がん登録データを用いて推定された生存率の解釈における考慮すべき点
- DCO(死亡情報のみで登録された患者)の割合を含めた登録データの質
- 生存率の推定方法に関連した限界
- 異なる群における生存率を比較する際の注意点
- わが国において、窒息に起因する院外心停止の約10%が餅によるものであった。
- 餅による院外心停止の多くは正月三が日に集中していた。
- 患者の予後改善のためには、周囲の人が一刻も早く窒息に気づき、119番通報することが重要である。
- 1990年代から2000年代にかけて、日本人子宮体がん患者の生存率が改善した。
- 類内膜腺癌以外の腺癌や癌肉腫の患者では短期生存率のみが改善していた。
- タキサン系およびプラチナ系併用化学療法の普及を含む医療の発展が生存率の改善に寄与している可能性が考えられる。
- 韓国では心房細動の有病率が増加している。
- 心房細動の有病率は男性で30歳、女性で60歳で増加する。
- 有病率の増加には高齢化のみならず心房細動の合併症の変化が寄与している可能性がある。
- ワーファリン治療率は依然として低い。
- がんサバイバーの勤務継続率は、復職後5年で48.5%であった。
- 勤務継続率は、復職後の一年間が急激な減少を認めた。
- 復職後の勤務継続率は、がん種により顕著な差を認めた。
Short Communication
Intensity of Leisure-Time Exercise and Risk of Depressive Symptoms Among Japanese Workers: A Cohort Study
Intensity of Leisure-Time Exercise and Risk of Depressive Symptoms Among Japanese Workers: A Cohort Study
- 本研究では、余暇運動強度と抑うつ症状発症との関連を検証した。
- ベースラインの抑うつ状態を含む潜在的な交絡要因を調整後、高強度のみ、あるいは高強度と中強度の運動を実施していた人では抑うつ症状発症リスクの低下を認めたが、中強度のみの運動を実施していた人ではリスク低下を認めなかった。
- 高強度の運動は抑うつ予防に役立つ可能性がある。
- 子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)は全国規模の出生コホート研究である。
- 我々は約10万組のお母さんとお子さんに、また接触できる範囲でお父さんにも、参加登録を依頼した。
- この論文では、お母さん、お父さんとその子どもについてのベースラインプロファイルをまとめた。
- 我々は、このエコチル調査参加者集団は日本の出生児を代表すると見なせる集団であると考えている。
Volume 28, Issue 1 (January 2018)
- 本メタ解析では、2型糖尿病遺伝的リスクの定量評価を行った。
- 1リスクアレルあたりの2型糖尿病罹患オッズは1.16であった。
- 1リスクアレルあたりの2型糖尿病発症オッズは1.10であった。
- この2型糖尿病のリスクアレルのエフェクトサイズは、body mass index増加0.58 kg/m2分にすぎない小さなものであることが分かった。
- レプチン/アディポネクチン比はMHOとMUOを見極める指標かもしれない。
- 異常なアディポカイン値はMHO児の高血圧リスク上昇と関連がある。
- “メタボリック的には健康”という言葉は、今後の研究では慎重に使うべきである。
- 女性の悪性黒色腫、基底細胞がん、有棘細胞がんは、それぞれ異なった紫外線曝露のプロファイルと関連している。
- 悪性黒色腫リスクは、25歳以前の日焼けの回数との関連が強かった。
- 基底細胞がんリスクは、余暇時の紫外線曝露と関連が強かった。
- 有棘細胞がんリスクは、主に全紫外線曝露と日常の紫外線曝露と関連していた。
- 高年齢の女性では血液型Oにおいて胃十二指腸潰瘍の罹患が高かった。
- 血液型O、ピロリ菌感染は胃十二指腸潰瘍発症と関連が認められた。
- 日本ナースヘルス研究参加者の自己申告血液型の正答率は高かった。
- 減塩・カリウム摂取に活用可能な自己測定機器が開発された。
- 我々のトライアルは機器の使用者と非使用者の間で尿Na/K比を比較した。
- 自己測定による介入で尿Na/K比は低減傾向を示した。
- 食習慣を改善する教育の併用によって、さらに大きな低減があるかもしれない。
- 非喫煙者では、受動喫煙はCIN1のリスク要因である。
- CIN1のリスクは受動喫煙の期間が長いほど高い。
- CINリスクに対する受動喫煙とHPV感染との相互作用はなかった。
- 急性期の脳梗塞患者における抗菌膀胱留置カテーテルの使用率は43%であった。
- 全体では、抗菌性カテーテルの使用と尿路感染症(UTI)発症との間に関連は認められなかった。
- インスリンを使用された糖尿病を有する患者においては、抗菌性カテーテルを使用した群で有意に尿路感染症の発生が少なかった。